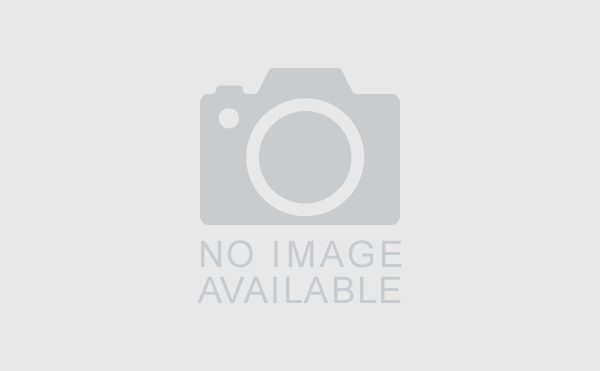ポジティブ心理学とは何か
理事見聞録#020
NPO日本プレゼンテーション協会
副理事長 太田哲二
前回、レジリエンスについてお話しさせていただきました。ここで少しポジティブ心理学について復習してみましょう。
写真はポジティブ心理学を提唱したペンシルバニア大学心理学教授の
マーチン・セリグマンです。

【ポジティブ心理学と普通の心理学との違い】
かつて「人の心を研究する」と言えば鬱のような精神疾患などマイナスの面のテーマばかリが中心でした。特に臨床心理学では人間のネガティブな側面に注目して「なぜだろう?」と追及する傾向が強くありました。「心の病の状態はどうして起こるのだろうか?」「どうすれば正常に戻すことができるのか?」というように原因や対策の研究に力を入れてきました。いまでもストレスが体に与える影響とか、うつ病の患者にはどのように対処すべきかといったマイナスの面の研究テーマを中心とした研究が盛んにおこなわれています。1998年ここに新しい風を吹き込んだのがマーティン・セリグマンというアメリカペンシルバニア大学の心理学者です。彼は人間の心の負の側面、則ち、心の病の状態に焦点を当てるのは研究の半分にしかすぎず、残りの半分、則ち、人の可能性や潜在力に光を当てる研究があってもいいのではないかと考え、「ポジティブ心理学」を提唱しました。そして「何が人生に幸せをもたらすのか?」をテーマにしようと心理学者たちに呼びかけたのです。その結果、様々な心理学者によって人生に幸せをもたらすもの、ウェルビーイング(身体や精神の良い状態)についての研究が行われ成果が共有されていきました。「ポジティブ心理学」はそうした研究の積み重ねで成り立っている心理学の一分野です。よくアンブレラ・タームと言いますが、ポジティブ心理学の傘の下には幸福感、ポジティブ感情、楽観性、人間関係、レジリエンス(困難を乗り越える力)ポジティブな組織などのたくさんの研究分野があります。これらはいずれも主観的な気持ち、個人の特徴、社会的な在り方などの観点から「幸せ(ウェルビーイング)」の源を追求します。従来の心理学の問いが「どうして心が病気になるんだろう?」、「どうして失敗するんだろう?」、「何が心を弱くするのだろう?」とうまくいかない理由に注目して原因を探るのに対してポジティブ心理学では「どうしてうまくいくんだろう?」「どうして幸せな気持ちでいられるんだろう?」、「どうして創造的で前向きになれるんだろう?」と物事が「うまくいく理由」に注目するのです。

【ポジティブ心理学とポジティブ思考(ポジティブシンキング)の違い】
「ポジティブ心理学ってポジティブシンキングのこと?」よく聞かれる質問です。ひと言でいうと違います。私達は「幸せでいるのが大切」と聞くと「いつでも明るく幸せそうでいなければいけないのか・・」としんどく感じる人もいるかもしれません。しかしそれはポジティシンキングの呪いにかかっているのです。ポジティブシンキングとポジティブ心理学は別物です。つらい気持ちに蓋をして何でもかんでも無理やりすぐにポジティブに捉えようとする必要はありません。自分が感じている内容をねじ曲げて解釈したり、自分の心に嘘をついたりすることは、自分を否定することになりますから、自己肯定感とは正反対です。つまりポジティブシンキングをいつも心がけることは人によっては大きなストレスの原因になり得るということです。心理学者のバーバラフレドリクソンは「偽りの笑顔」は心疾患を起こす可能性を高めるという研究結果を報告しています。
二つの違いに関してもう一つ言えることは学術的な裏付けがあるかどうかということです。ポジティブ心理学は科学ですから再現性があります。すなわち有意差があるかないかのしっかりした統計処理をして学会に報告され、科学的に実証されたデータをもとにして議論されるのです。先ほどの「偽りの笑顔」の例ですと、「偽りの笑顔」のグループと「本物の笑顔」のグループの人たちを集めてきて、血圧や心臓や脳の血管の動脈硬化を見たり、血液検査をして差があるかどうかの統計処理をしています。ある程度の人数がないと統計的な有意差は出ませんのでサンプルを集めるのも大変ですし、そもそも「本物の笑顔」と「偽りの笑顔」をどこで区別するのかも定義する必要があります。皆さん方は違いが判りますか?「本物の笑顔」は目が笑っているのです。ですから、目じりにしわが寄ります。「作り笑い」ですと口は笑っているように見えますが目が笑っていません。「モナリザの微笑み」が口では笑っているのですが目が笑っていないので謎の微笑みと言われていましたが、統計上は「偽りの微笑み」に分類しています。ほかにもポジティブな感情と寿命の関係、組織の研究ですと組織のメンバーの強みを活かしたチームとそうでないチームのメンバーのやる気や離職率に差があるかどうかに関しても研究されています。修道院の尼さんの研究では彼女たちの日記から日記にポジティブな記載の多い尼さんのグループはそうでないグループに比べて明らかに長寿だったということが証明されています。また、強みを活かしたグループは働く意欲を上げ離職率を減らすことが証明されています。このようにポジティブ心理学ではしっかりした統計データをもとにしたエビデンス(証拠)を持っていますが、ポジティブシンキングでは自己啓発系に多いのですが「良いことを考えれば良いことを引き寄せる」などポジティブな考え方をすることを勧めます。私はポジティブシンキング自体は嫌いではありませんが、エビデンスの点が不足しているのと、なんでもポジティブに考えなければならないと、無理やりにポジティブに考えることにより弊害があるということに注意する必要があると思っています。ポジティブというところでは一致していますが実は大きく違うのだということを理解していたければと思います。
最後にもう一つポジティブ心理学に関しての誤解についてお話しします。ポジティブ心理学では「極楽とんぼ」のようにポジティブなことしか扱わないかと言えばそれは間違いです。人間の感情はポジティブなものネガティブなものがありネガティブが必ずしも悪いことではありません。人間は古代から猛獣と出会えば「怖い」という気持ちが起こり逃げるという行動をとります。人間はネガティブな感情のおかげで生き延びてきたとも言えます。ポジティブ心理学ではポジティブとネガティブを含めてトータルで人間ですので、当然ながらネガティブな側面にも焦点を当てて研究します。有名な研究に人がしっかりと成果を上げるにはポジティブな感情だけでは不十分でネガティブな感情も必要である、そして、その比率はポジティブ感情3に対してネガティブ感情1でバランスが取れることを先ほど紹介しました心理学者のバーバラフレドリクソンが研究成果として発表しています。例えば部下や後輩を一つ叱ったら三つフォローしてちょうどよいわけです。このようにポチティブ心理学ではネガティブな側面に関しても研究していますが、誤解されることが多いので、ポジティブ心理学の提唱者、マーチン・セリグマンは、一時「ポジティブ心理学」という名前を「バランス心理学」という名前に変えようかと、真剣に考えたという逸話も残っています。
以上、ポジティブ心理学についてこれまでの心理学やポジティブシンキングと比較しながら説明させていただきました。
(以上)